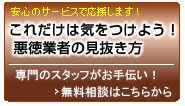第6章 日本社会への順化は可能か[3]
-
-->
-
第6章 日本社会への順化は可能か[3]
他民族が日本人を強くする
ここからは日本について考えてみる。そもそも日本人とは何なのか考えてみたことはあるだろうか。堅くいえば「日本に定住する日本国籍の人」のことだろう。外国生まれで日本に帰化が認められる人も実は、毎年1万4千人前後いる。肌と目の色がさまざまな日本人が生まれてきている。
2009年、妻とアメリカに滞在していた時、ワシントンで開かれたパーティーで、ある年配のカップルと知り合いになった。旦那さんはベトナム系アメリカ人、奥さんは米国生まれだった。
夫に寄り添うようにしていた奥さんは「国際結婚が多いアメリカでも、アジア系の男性と結婚するのは勇気がいることだった」と話した。50年前の話だから、それは偏見も強かっただろう。オバマ米大統領の母(白人)と父(黒人)が結婚した半世紀前は白人黒人の結婚は、1000組に1組しかなかったというデータさえある。
旦那さんは米国に留学に来ていた。それでも思い切って結婚して良かったと彼女は言う。
「ベトナムの文化や言葉を学べたし、アジアのいろいろな国の人と知り合えたから」。二人の間に生まれた一人娘は、今度はセルビアというヨーロッパの国から来た男性と結婚することになった。
アメリカの国際結婚は、もはや当たり前のことだ。だれも珍しがらない。それが、アメリカの強みになっている。もちろん、アメリカの市民権を取る目的で、比較的年齢の高い米国籍の男性に近寄る外国人女性もいる。それはあくまでも個人の選択だ。
「アメリカ人」という概念自体「日本人」とは多少違う。アメリカ人とは一つの民族を指すのではなく、世界からアメリカを目指して集まって来て、市民権を得た人を指す言葉になっている。もちろん肌の色も、目の色もバラバラだ。それをみんなが自然に受け止めている。
日本と米国は似ている部分もある。たとえばコンビニやマクドナルドに行けば、米国では南米の人がてきぱきと働いている。日本では中国や韓国からの若者が日本語で応対してくれる。否応なしに日本も、外国人を「日本人」のカテゴリーの一つとして取り込んでいく社会に変わっていくのではないかと思う。
経済に活気
中国から妻として日本にくる女性たちは経済移民と考えてもいいだろう。大半は普通の主婦に収まり、慣れないながらも日本の社会にとけ込んでいく。
中には日本企業に入って日中間のビジネスの中心になったり、自分で会社を興して成功する人もいる。言葉や習慣の違いを乗り越えてたくましく生きている女性たちもいる。
2008年末、中国の新聞「国際先駆導報」が興味深い記事を配信した。この新聞は、中国国営新華社が発行する新聞で、この通信社の記者が直接執筆している。
中国の女性たちが、日本の社会で活躍しているという内容だ。2人登場する。1人は孫犁冰さん。東北部の瀋陽出身である。
新潟県新潟市のある通訳会社の社長で、2つ目の博士号を取得するため新潟大学で学んでいる。すでに女の子が1人いる。通訳会社を立ち上げ、日中間のさまざまな会議や活動の通訳を手がけるほか、地元の教育機関で中国語教師としても活動し、中国に興味のある日本人に中国語や中国文化を教えている。
もう1人は、山形県のある役場で「生活支援通訳員」として働いている人のことだ。常勤嘱託職員として、生活・育児・医療などの面で、家庭や地元社会での外国人妻のコミュニケーションを積極的に手助けし、文化の違いから来る面倒やトラブルを解決するのが仕事だ。
結論としてこの新聞は「中国人花嫁はその勤勉さ、伝統、強靱さによって、日本社会で次第に積極的なパワーを示し始めている」と書いている。
枠にはめたがる日本人
この記事に出てくる孫さんに話を聞いてみた。
彼女は翻訳会社社長、二百人の生徒を教える中国語教師、大学院生、短大の非常勤講師、娘の母親ーと、一人五役をこなす。
ハルビン市生まれで、十八年前に来日し、私費留学生として新潟大学に入学した。天津から新潟まで船と夜行列車を乗り継いで六十時間かかった。
通訳として働いていた会社で夫と知り合い結婚した。「日本語がうまく話せない」というコンプレックスをバネに、二〇〇五年に翻訳会社を設立。中、英、ロ、韓国語スタッフを抱える。
大学院では比較言語学で二つ目の博士号を目指す。テーマはやはり「中国語と日本語」だ。
「漢字は中国人と日本人の絆です。中国語の漢字の読み方は原則的に一つで、文法も比較的簡単。だから中国語は、もう一つ漢字の読み方を覚えるだけでマスターできるんです」と強調した。
地元の新聞に日本語で寄稿した経験もあり、「中国のソフトパワー戦略」と題した本も出版する予定だ。
孫さんは、日本の製品を上海の富裕層向けに販売するため、会社をつくり、旦那さんが上海に常駐するなど、事業の拡大を図る一方、同じ国際結婚家庭の喧嘩仲裁も引き受けている。そこで感じたのは日本人が「外国人慣れ」していないということだ。「たとえば、大根の皮の剥き方が気にくわないと姑さんが奥さんを批判する。そこまで求めなくてもいいじゃないですか。時には中国風の料理方法を楽しんで欲しい。枠をはめようとしたら必ずうまく行かない」と指摘する。
キムチで成功
山形県の北部・最上地方は、かつて村をあげて国際結婚が奨励された地域だ。ここでも新しい産業が生まれている。韓国から嫁入りした女性の発案で戸沢キムチが開発された。これを中心に韓国館と名付けられた施設が誕生し、今では韓国物産を製造販売する観光名所になっている。
阿部梅子(金梅永)さん(49)は、地元では「梅ちゃん」の愛称で通っている。ソウルでOLをしていたが、友人の紹介でたまたま日本人の男性とお見合いし、結婚を決めた。ソウルから山形県朝日村(現・鶴岡市)に来たのが一九九一年。周囲には家がほとんどない農村だった。
家の近くの工場に働きに出た。友達づくりのつもりで職場の同僚に手作りキムチを配ったという。
「最初は辛すぎだとか、ニンニク効き過ぎだ」との辛口評価だったが、「そのうち病みつきになったらしくて、売ってほしいと言われた」(阿部さん)。
自信をつけ、地元で「うめちゃんキムチ本舗」と名づけた会社を設立。韓国料理店五軒を経営、都内だけでも二百近いスーパーに商品を卸す。高級スーパー成城石井にも並んでいる。
売り上げが年一億円に迫る今もチマ・チョゴリを着て全国の物産展に参加し、自社製品を売る。スケジュールはいっぱいで、連日日本中を飛び回る。
社員は国際結婚の韓国、中国人女性が二十人以上。「私の給料の半分をあげればいいやと思って引き受けていたら、こんなに増えてしまった」と笑った。
商品開発にも熱心だ。最近完成したのが山形特産を生かしたミョウガキムチ。コンニャク入り健康キムチは加工に時間がかかり、製品化をあきらめた。
全国の自治体から、外国人の能力を生かす方法について講演依頼が相次ぐ。「日本人は一生懸命がんばる外国人にはとっても優しい。仲良くできる」が持論だ。
彼女たちが日本に持ち込んでくる外国文化は、日本の財産になる。国際結婚がもたらす光の部分だと思う。
企業の中核から大富豪まで
企業も中国人のパワーに注目している。2009年に朝日新聞が、化粧品大手資生堂に勤務する華黛臨さんを取り上げていた。華さんは中国向けの高級化粧品の担当だ。福建省出身で、日本の大学でマーケティングを学んだ。いまは中国人女性の好みに合わせた化粧品の販売に当たる。
4章で紹介した中国人の小説家の楊逸さんは、中国ハルビン市生まれ。お茶の水女子大学文教育学部を卒業した。新聞社勤務などを経て、 『ワンちゃん』で第105回文學界新人賞受賞し、『時が滲む朝』で第139回芥川賞を受賞した。選考委員の1人、小説家の高樹のぶ子氏は「中国の経済はいまや否応なく日本に大波をもたらしているが、経済だけではなく、文学においても、生活実感と問題意識を搭載した中国の重戦車の越境に、どう立ち向かえるのか。今回の受賞が日本文学に突きつけているものは大きい」と述べ、外国人が日本語で書いた小説にショックを受けたことを明らかにしている。
中国人女性のタフさは、一代で財を成した女性富豪の多さでも証明されている。2010年6月、米経済誌フォーブスが発表した世界の総資産10億ドル以上の大富豪1000人超の中で、相続によらずに一代で財を築いた女性企業家は14人だったが、そのうちの7人が中国人女性だった。このリストの中で女性が占める割合はわずか2%だった。
このニュースを転電した中国の新華社通信は「成功した14人の女性のうち半数が中国人女性であるということは、中国が女性の起業家にとって最も適した環境だということ」と自画自賛した。女性の1位は呉亜軍(44歳・不動産開発)は39億ドル(約3500億円)という人だった。
もう1つ、米フォーブス誌が発表した「世界の富豪夫人トップ10」によるとウオールストリート・ジャーナルなどを抱えるメディアグループの総帥、マードック氏の妻ウェンディー・デンさんが、1位となった。
ウェンディー・デンさんは1969年、中国江蘇省生まれ。99年に37歳年上のマードック氏と結婚、2女をもうけた。米イェール大でMBAを取得するほどの才女だという。
ちなみに2位はメリンダ・ゲイツ、米マイクロソフト社の共同創業者ビル・ゲイツ氏の奥さんだった。